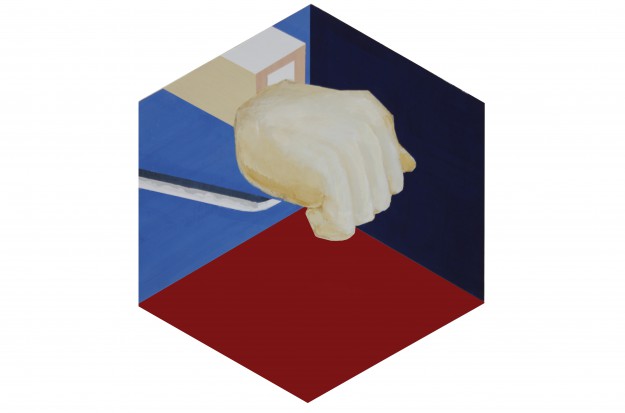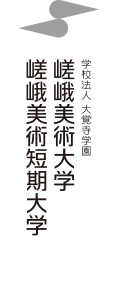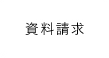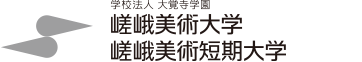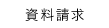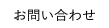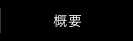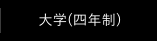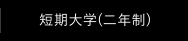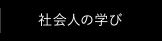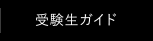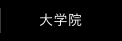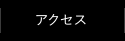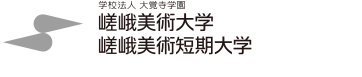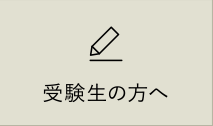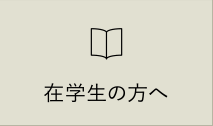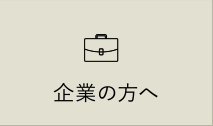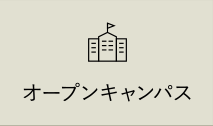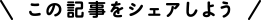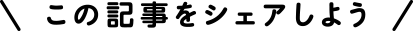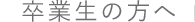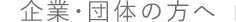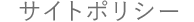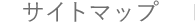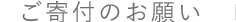前回の本コラム文末で、私は日本刀の美しさをおもいっきり持ち上げたのだが、もう少し説明を加えるべきかとおもう。
人間がつくりだしたありとあらゆるモノの中で、日本刀の美しさは格別だと感じている。
「折れず曲がらずよく斬れる」。三拍子そろってこそ優れた日本刀、というのが定説となっている。刀剣も、まず基本的には道具なのだから、求められる機能にきっちりと応えなければならないのは当然だ。
刀剣は、「斬る」という基本的機能において、肉を一刀両断にし、究極は死をもたらす道具である。生と死を背負ったところに、なまぬるい日常感覚にはない冷厳な役割が意識されているのである。ここに独自の真剣で冷徹な美がわき上がる源泉があるとおもえる。
人殺しの道具にグッドデザインを求めたり、美術工芸品にみる感動を見出すこと自体、納得しがたいという見解もありうるだろう。美と倫理の関係を、深いものとしてつなぐか、あっさり、そこは超えて、われわれ人間の認識とそれに基づく評価という作業を無条件に許すか。
しなやかな心材として炭素の少ない心鉄(しんがね)を、炭素の多い硬い皮鉄(かわがね)が包む構造になっているところに刀剣の「折れない」と「曲がらない」という対立する要件を解消する秘密がある。皮鉄が薄くなった端部が刃(鉄)であり、ここが焼き入れされてより硬くなる。
それから、刀鍛冶の仕事ぶりを紹介する映像などでおなじみの「折り返し鍛錬」も、日本刀の優れた特性を生み出している重要な作業となっている。真っ赤な鉄をたたいて、たたいて、不純物を排除しながら、炭素量の調整をしつつ、何度も折り返して多重な層をつくっていくのである。10回折り返すと1024層にもなる。
刀工は、完全な統御不能の火をつかいながら鋼を、満足のいく形に成形していく。高度な技術を自己のものとしながらも、結局どうなるのかわかない要因に対しては祈りで対処するしかない。
刀剣マニアは種々の逸話と名刀を結びつけ、いわれ自体を楽しむ傾向があるようだが、それも日本刀のもつ美に引きつけられた武将たちの評価の目を後代の人間に伝える役割とみれば、楽しめる。
逸話1。名刀への執念の強く、無類の刀剣蒐集家であった秀吉が、もっとも愛蔵したのが粟田口藤四郎吉光の太刀。吉光は正宗と並ぶ最高峰の名工。小柄な体格であった秀吉は、自分の体格に合わせて、刃長が2尺8寸3分(約86cm)あった一期一振を、2尺2寸7分(約69cm)に磨上げた。「一期一振」と呼ばれる短刀にリメークしたのだ。
逸話2。家康が死の直前に「ソハヤノツルキを久能山東照宮に奉納するように」命じた。筑後の刀匠三池光世の作といわれているこの太刀に、家康は豊臣秀頼方の残党封じがねらいとおもわれている。
(『日本刀』河出書房新社等を参照した)
刀剣の美を成している、並々ならぬ高度な製作技術、それを修得した刀工の清澄な決意と人間的洗練、死への誘いを含みもった宗教的存在感が、その美を例外的なものにしている、とおもえるのである。
カット: 芸術学部 油画分野3回生 得居直樹さん