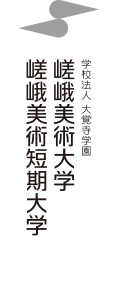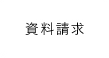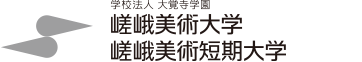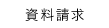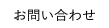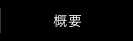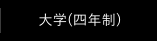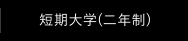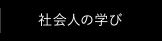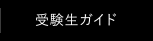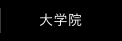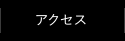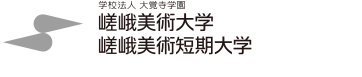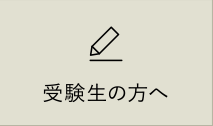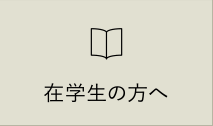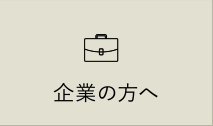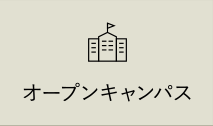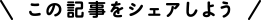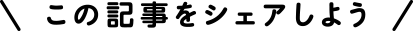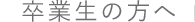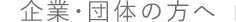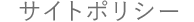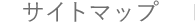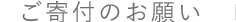内から「飛び出してくるものがある」というとき、そのものが、ひとりの人間から出て、他者の目にふれたり、耳にとどいたとするなら、それは表現物と呼べるものだろうか。
唾をはいた。汗をかいた。便を排出した。これらは、ふつうには表現物とはみなされない傾向のものである。しかし、唾、汗、便という概念(一般に受け入れられている認識)を、あえて特別な記号として作品化することは可能である。つまり、排泄物も創作の素材となる。
ピエロ・マンゾーニの「芸術家の糞」は彼自身のうんちが材料となっている、よく知られる作品である。自身の排泄物を「30グラム、自然保存」と記したラベルを貼付けした缶詰は、当日の30グラムの金の相場で売られた。
ミリー・ブラウンはゲロをキャンバスに塗り込めていく作品をつくる。池内美絵は、自身の生理の血で染めた布や精液を拭き取ったティッシュで作品をつくる。
排泄物が即作品ではない。ましてや、排泄行為が即創作になるとは認めがたい。内から外に出るものがあっても、これは創作である、という意志が創作者自身においてはっきりと自覚されている前提が必要である。
生物は自己の体内に保留しているものについては、自己の一部として親和的な態度をとる。腸内に留まる「うんち」(内にあるときは生体内滞留物でしかない)は不潔ではない。自分の一部という範疇に受け入れる。しかし、それが外に排出された瞬間、不潔な汚物とみなされ、自分とのかかわりを嫌う。さきほどまで口にあった食べ物も、うっかり吹き出せば、不快な汚物に豹変する。いや、モノは変わらないのだが、その名称、概念を変えるのは、われわれの意識の仕事である。
表現が成り立つには、内における外への「送り出し」の決意、あるいは意欲がまず求められる。とすれば、内に限りない美の宝庫を抱えているひとがいても、表現欲求をもたないかぎり創作者にはなれない。
存在そのものが美しいひとがいる、とする。多くのひとが、そのひとに魅了されても、そのひとを創作物としてはみないだろうし、当人の創造的な営みの成果によると認めることもないだろう。幸運がもたらした美、あるいは、そのような美を生み出した創造主の存在を讃えることはあっても。
舞踊家田中泯は、踊りの動きがもたらす視覚的センセーションを表現の目的とするよりも、彼の肉体そのものの存在に語らせようという意図をもつ創作者とおもえる。彼の生命自身が、そのエネルギーを発散している姿に表現が含まれているかのごとく。
田中は、「成長を人生の目的としないオトナ」(『僕はずっと裸だった』、2011)として、生のエネルギーを内に留めるカラダを尊重してきた。
田中の舞踏は、カラダの存在そのものを表現の素材としているというストイックな一面をもっているようにみえつつ、カラダを支えている心霊、あるいは生命エネルギーの自発的な運動にゆだねられているようでもある。
牛が自然を見る事は牛が自分を見る事だ
外を見ると一緒に内が見え
内を見ると一緒に外が見える
高村光太郎『道程』、牛(1913年)
芸術の力が内と外の交流を正しくはたすとき、自他の区別や対立が消散して、自他一如の境地をもたらす。
われわれの内には、頭脳の支配下にある知能(思考活動,mind)には計り知れない知性(intelligence)の無限大空間があり、芸術の力は、それに気づかせてくれる力なのだとおもう。つくづく有り難い力である。
芸術の力についての学長コラムは今回を持って終了し、次回からは専任教員によるリレーコラムとなります。