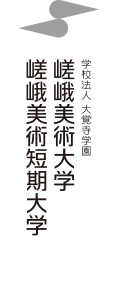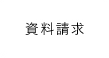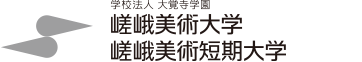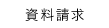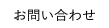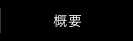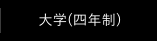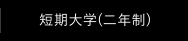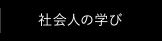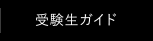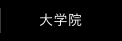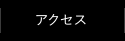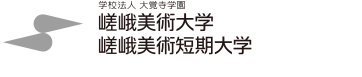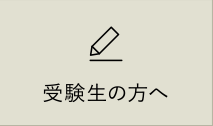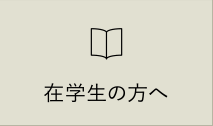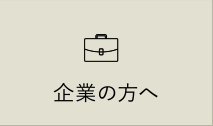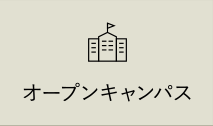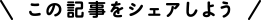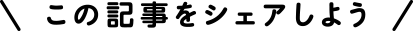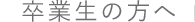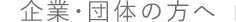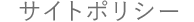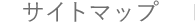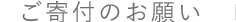学長の後を引き継いで本学専任教員がリレー形式でこのコラムを担当することになった。教育・研究・社会貢献という大学の三つの使命のうち、後者ふたつを扱う「嵯峨芸術センター」の長としてリレー・コラムの最初の担当を仰せつかったが、「先鋒」というより「露払い」程度のものという気持ちで、後に続く方々のベースになれることを願っている。
さて、ものごとを複雑に考えるのがもともと苦手なたちなのでなるべく話を単純化して書こうと思う。まずは「芸術の力とは何か」ということではなく「芸術に力があるのか」ということについて考えてみたい。芸術に力が無いのなら「芸術の力とは何か」という問い自体が消滅して無駄な労力を使わずに済むからだ。
島本浣氏と岸文和氏による『絵画の探偵術』(昭和堂、1995年)は、美術(史)を学ぼうとする者にとってたいへん好ましい書物で学生によく推薦するのだが、この冒頭に絵画が何をしているのかということが端的に書かれている。そのなかに「絵画は何かを物語っている」、「絵画は誰かを讃えている」、「絵画は何かを記録している」というものがある。つまり絵画は「物語る力」「讃える力」そして「記録する力」を持っているわけだ。この点について、彫刻はもちろん文芸や音楽にもそうした力があるということに異論はないと思う。
いわゆる《アレクサンダー・モザイク》(国立考古学博物館、ナポリ)やゴヤの《マドリード、1808年5月3日》(プラド美術館、マドリード)は出来事を強く物語っているし、《コンスタンティヌス大帝像》(カピトリーノ博物館、ローマ)や上野の《西郷隆盛》はその巨大な威容で彼らのさまざまな業績を讃えている。高橋由一が東北各地の景観を描いたのは土木県令三島通庸の事蹟を記録する意味合いがあった。
これでひとまず最初の問への解答は得た。ただ問題はまだ数限りなく残っている。実は『絵画の探偵術』で例示された作品も、いま私があげた作品も、いわゆる「伝統的芸術」の範疇のものばかりなのである。この解答は現代芸術にはあてはまらないのだろうか。
ハンス・ベルティングの名著『美術史の終焉』(元木幸一訳、勁草書房、1991年)の冒頭には、エルヴェ・フィシェルが1979年にパリのポンピドゥ・センターで行ったパフォーマンスについて述べられている。いささか長くなるが引用してみよう。
”フィシェルは左から右へ観衆の前をゆっくり歩く。彼は花模様の刺繍のあるインド風の白シャツと緑の上着を身につけている。彼は目の高さに張られた白いコードを片手にもち、それを頼りに進む。もう一方の手にはマイクをもち、一歩進むたびにそれで話す。「美術の歴史は神話的な起源をもつ。魔術、目、時代、取っ手、イスム、イスム、イスム、イスム、イスム、ネオイスム、―的、やっ、イオン、この、ポップ、それっ、キッチュ、喘息、イスム、芸術、この、チック、タック、チック。(中略)」
コードのちょうど中間の一歩手前で立ち止まり、「この喘息時代の最後に生まれた、単なる美術家にすぎない私は、一九七九年のこの日、《美術の歴史は終わりを告げる》と確信し、宣言する」と言う。もう一歩踏み出してそのコードを切り、また言う。「私がこのコードを切った瞬間が美術の歴史における最後の事件であった。」コードの半分を床に落として付け加える。「この落とされた線をまっすぐ延長したところで、思考の無益な幻影にすぎなかろう。」
ついでフィシェルはコードの残り半分を落とし、「これからは幾何学的幻影から解放され、現代のエネルギーに目を向け、我々は
1979年のこの「預言」は恐ろしいほどに的中したと思う。たとえば先年の「PARASOPHIA 京都国際現代芸術祭2015」に眞島竜男が「作品」として出品した「近代美術」「フェノロサ」など数々のダイアグラムはチャート化されたアートについての「テキスト」が「アート」として提示された、究極の「メタ・アート」だったといえる。
さらにベルティングは、「現代美術を伝統的美術から区別するあの社会的役割の欠如」とか、メイヤー・シャピロを引用して「絵画はもはやコミュニケーションには利用できず、むしろ意識的にマス・コミュニケーションに抵抗しさえした」とも語る(ちなみに引用元のシャピロは「普通の手段では絵からメッセージをひき出すことはできない。」とまで言う)。ベルティングの原著の初版が1983年でシャピロにいたっては1957年の文章だから、やはり現代芸術、少なくとも現代美術は20世紀のうちから大幅に姿を変えたのだと私自身も考えている。
では、現代の芸術は力を持たないのか、あるいはその力とはどんなものなのだろうか。社会的な役割を持たず、コミュニケーションの手段にもならない(だからこそ、ますます「アーティスト・ステイトメント」とかいうテキストが幅をきかせるようになっている)芸術にどんな力があるというのか。
沖縄の基地問題や従軍慰安婦問題、原発問題などについて考えるたびに、世界はますます全体主義的な風潮へと向かっていると強く思う。現場でも、ときにはそれを報道するマスコミでも、こうした問題に直面して大きな力の前でなすすべもなく、ただ語ることしかできないひとりひとりの小さな声が隠蔽されたり無視されたりしている。
もしかしたら現代の芸術というものは、そうした小さな声なのかもしれない。作家の存在を示すバウチャー標本のようなものなのかもしれない。だからといって、その価値が低いと言うつもりはない。それは政治や宗教、さまざまな文化から切り離されたきわめて個人的なものではあるが、そうした「構築されざるもの」の「存在の金切り声」(北田暁大)であって、それを誰も抑圧したり無視したりする権利はないのである。むしろ一人の人間がたしかに存在したということを明確に証明できる大きな力を持っていると考えたいと思うのである。
最後に。いわゆる「デザイン」や具象の美術なんかはどうなるのよ、という声が聞こえてきそうですが、そこは次回に書くつもりです。あしからず。