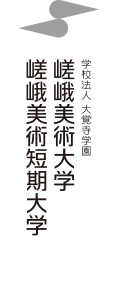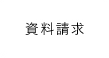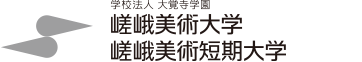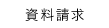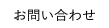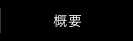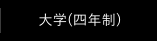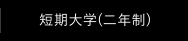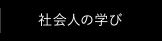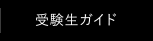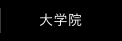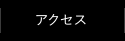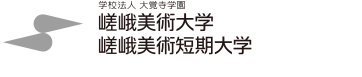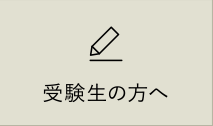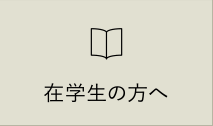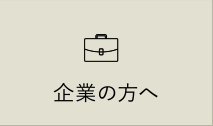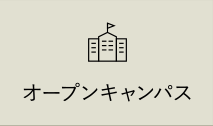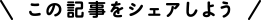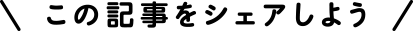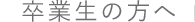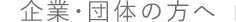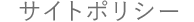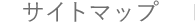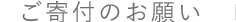ものすごく漠然としたタイトルではあるが、前回にデザインと具象美術について書くと宣言した以上、書かねばなるまい。ただ、具象のことはちょっとおいておく。
「デザインとファイン・アート(アーツが正しいけれど、みんな単数形で言うので)は違うのだ!」「デザイン教育のメソッドとファイン・アート教育のメソッドは違うのだ!」という声をよく聞く。こちらは漠然とした話ではない。カリキュラムのことになると、職場でそういう趣旨のことが声高に語られる。ほんとうにそうなのだろうか?
こういうときは原点回帰。ごくごく基本的な書物を調べてみることにした。まずは、おそらく「デザイン史」を勉強しようとする日本人(学生)のほとんどが手に取るであろう、阿部公正監修の『[カラー版]世界デザイン史』(美術出版社、1995年)。「デザイン史は美術史と密接な関係をもっている。」「だが、デザインは美術と異なる面をもつものである以上、デザイン史は、美術史の単なる応用部門として記述、理解されるわけにはいかない。」(9頁)とある。つまり、ここではデザインは美術と関係はあるが「異なる面をもつ」と理解されている。つづけよう。同じ書物にはこうもあった。「また、デザイン史は『近代』デザイン史として記述される。」(9頁)これにはビックリだ。デザイン史=近代デザイン史だと言っているのである。近代より前に、デザインは存在しないことが明言されているのに等しい。それにしたがって、この書物ではウィリアム・モリス(1834-96)の業績から記述が始まる。
次はデザイン史フォーラム編の『国際デザイン史』(思文閣出版、2001年)。序文の冒頭を引用する。「近代デザイン史を扱ったわが国の出版物は…」。
もうたくさんだ。いきなり「近代」である。どうもこの「近代」が曲者のようだ。
鍵が見えてきたところで、少し専門的な文献に移ってみた。世界最大のといってもよいGrove DictionariesのThe Dictionary of Art(New York 1996)をベースにしたGrove Art Onlineの「デザイン」の項目から。
この項目では「20世紀」とはっきり述べているが、ようは「近代」において「デザイン」という語に意味上の変化が起きたということだ。
この変化についてさらに詳しく説明してくれていたのが、その名も『デザイン』(リブロポート、1988年)という秀逸な論文集に含まれる、まさに「アートとデザイン」というタイトルのマルク・ル・ボットの論文だった。
「美的対象の場」における造形化が「アート」で「日用品や共同体の場」における「造形化」が「デザイン」ということになろう。その造形化の目的は根本的には同じであったが、それが分化してしまった。ル・ボットはその分化のプロセスを探ろうというのである。
分化の始まりを「産業社会の到来」に見る彼の主張は平凡なものだが、それを「テクニック」という語の意味の変化から跡づける点は面白かった。「第一次産業革命」により分業化が進み、「実践のあらゆる分野に生産性の掟が徐々に広がって」いった結果、「芸術と技術の対立、美的対象の生産と日用品の生産の対立」がおこり、「技術的な」という形容詞だった“technique”が名詞の「技術」としても使われるようになったというのだ。そして、「産業社会」が「実際にものを作り出す実践的な仕事(手や道具による
ル・ボットはこのように、産業社会の到来によってデザインという新ジャンルが成立したとする。しかしこれを逆に見ることはできないだろうか。一部の「アート」が「ファイン・アーツ」から分離してしまい、むしろデザインの方が「ファイン・アーツ」陣営に残っているのではないかという見方だ。近代の産業革命はたしかに人間の生活を大きく変えた。だが、古代ローマではコンクリートを用いたことで、ギリシアではできなかったアーチやドームを易々と産みだしたし、油彩やカンヴァスの普及がもたらした絵画の変化は大きい。チューブの発明は―産業革命のただなかでのことだったが―画家をアトリエから解放した。つまり、技術の展開は確実に制作の現場を変え、作品の様式にまで影響をおよぼしてきたのである。近代の産業社会はその展開の度合いがたしかにおおきかった。それに応じて社会やそれを構成する人間と切り結び、かつてのアートがそうであったように「社会的
「いくらなんでもそれは言い過ぎだ」と思われる方も多いだろう。自分もすべてのアートがその道を進んでいるとは思わない。あくまでも「一部のアート」であり、「みずから分離の道を選んだ」アートについて言っているのだ。問題は、相当の時間の経過のせいで重大な選択の時を忘れてしまい、分離の結果としてのアートこそがアートなのであると思い込んでしまったアーティストが産まれ、そのアーティストたちが「矮小化」し「貧困化」したアートを、さも素晴らしいもののように喧伝し、後進にもそれをすり込んでいるところにある。
ちょっと筆がすべった。アートとデザイン、かつてこれらは同一の目的を持っていた。それが近代にいたって分化してしまった。自己閉塞の道を選んだものには「アート」の名が与えられ、順応の道を選んだものに「デザイン」の名がついた。このことを典型的に示しているのが、近年よく聞かれるようになった「建築デザイン」「建築デザイナー」という語である。かつて建築はファイン・アーツの先頭を行く存在だった。美術史の書物は時代ごとに「建築・彫刻・絵画」の順で記述されていた。建築はその中で人間が活動するゆえに、必然的に人・社会との関わりを避けられない。ところが近代以降は「社会的
分離を選んだアートは、それでよいのだろうか。「矮小化」「貧困化」を食い止められないのだろうか。またデザインとの蜜月関係は復活しないのだろうか。私は、それはあると信じている。答は単純である。
ル・ボットの言葉にまた戻ろう。「なにか、あるものが可視的な形をとるということは、美的対象の場においても、また日用品や共同体の場においても、おこることである。このような造形化は、少なくとも社会空間の全体とかかわり、歴史的な制度慣習という価値を持つ。」ひとつは「造形化」だ。もうひとつが「社会空間の全体とかかわる」ということだ。
アート陣営もデザイン陣営も「造形力」を高めること。いたずらにデュシャンのまねをする必要はない―デュシャンの二番煎じの枠をどう出るというのだ―。テキストに頼りすぎるのもよくない―芥川やカルヴィーノや一流コメディアンに勝てますか―。思い通りの線を描き、面を作る訓練、それの前提となる思い通りの線/面を知る訓練。これをおろそかにしてはいけない。
アート陣営もデザイン陣営も「社会空間」とそれを構成する人間を深く、広く理解すること。ひとりでじっと考えるのではなく、多くの人の声を聞くこと。それには本を読むことが一番。図書館を考えてみればよい。そこには過去/現在(ときには予言)の、実際の/架空の、地球の/宇宙の、ありとあらゆる世界が詰まっている。
そうしないと芸術―もちろんファイン・アーツとデザインを包含する―は力を発揮することができなくなり、芸大はもちろんのこと、ギャラリーも美術館もなくなるか、単なる化石の陳列場と化してしまうだろう。