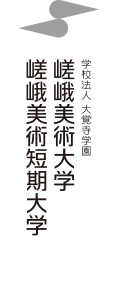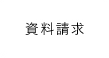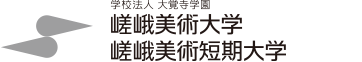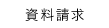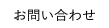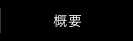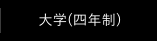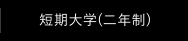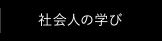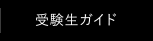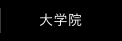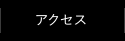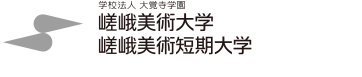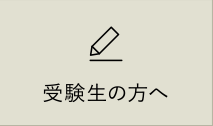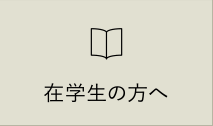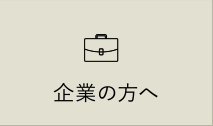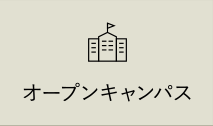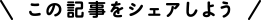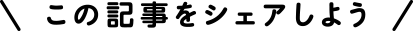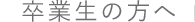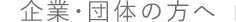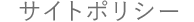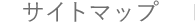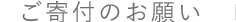「芸術の力」。“Power of Art”。“Power”である。「能力」である。相手の圧倒的な能力の前には屈服しなければならない時がある。
美術史家の端くれとして、ほとんどの「芸術」に対して言葉で対抗する。サウンド/ノイズやイメージ、テクストに対して。驚異的なパワーに直面し、それでもなんとか踏みとどまれる時もある。香月泰男のシベリア・シリーズはそんな作品だ。C.S.ルイスの『ナルニア国物語』のシリーズもそうだ。ギリギリで自分が保てる。鑑賞者というか批評家のスタンスをなんとか保つことができる。
ところが―正直に言うが―対応できない時がある。そんなときはどうしようもない。享受を拒否せざるを得ない時さえもある。あまりにも苦しく、「やめてくれ」と叫ぶほかはない。たとえば、ベルゴニョーネ。ロンバルディア地方で活躍したルネサンス期の、ふつうには「レオナルド派」と言われる画家だ。「妖艶」とか「幽遠」とか言ってみてもかなわない。たとえば、いしいしんじ。ある時期までは流れるようについていけた。『みずうみ』からはきつい。あまりにも強烈すぎる。だが、蒼暗い靄のような、しかし究極的にはこれ以上無いほどに透き通り澄明な「気」に包まれて、自分自身もその場にいるように、しかしどうしても最後のところに手が届かないような、そういう感覚を味わいながら少しずつ少しずつ読み進めるしかない。
これは「力」以外の何ものでもない。あきらめるしかない強大な力である。もちろんそうしたものは、こちらをねじ伏せようとしているのではない。言うなればただそこにたたずんでいるだけである。こちらが好きこのんでその場に身をゆだねに行っているだけである。鑑賞などできるはずもない。まさに身をゆだねる。五体投地のような心境かもしれない。ただ敗北するためにだけ、その場に赴くのだ。そしてそれに包まれながら、自らの闇の部分が明るみに曝けだされ、それでもそれでよいと感じ、もはやなけなしの全感覚が研ぎ澄まされていく自分を知ることができる。
芸術作品の体裁を整えているもののなかには、こちらをねじ伏せようとしているものもあると思う。これでもかと言わんばかりに、力(この場合はforce)を振りかざしてくる。思えば、古代のコンスタンスティヌス大帝の巨像もそのようなものだったのだろう。システィーナ礼拝堂のミケランジェロもそんな感じがする。ローマの街中にそびえ立つヴィットーリオ・エマヌエーレ二世の記念堂もだ。
ところで、自分自身は美術作品に罪は無いと思っているが、圧政をしく者の趣味にたまたま合ってしまった作家の作品には、かなりの共通性がある。まずは筋骨隆々とした肉体的な力を誇示する男性像。そして従順で華奢な、かすかな媚態と豊満とはいえない―力を発してはいけないから―肢体の女性像。その典型的な例が、ナチ政権下でヒトラーの寵愛を受けた彫刻家ヨーゼフ・トーラク(Josef Thorak)、アルノ・ブレーカー(Arno Breker)やゲオルク・コルベ(Georg Kolbe)、そして画家アドルフ・ツィーグラー(Adolf Ziegler)たちの作品であったり、ローマの通称「大理石のスタジアム」に並ぶ彫刻群であったりする。
政治に寵愛される作品は、その政権の理想的国民像が重ねられているといってよいだろう。この「理想的」というのがくせ者だ。個と個の集まりから生まれる多様性を一気に捨象し、たったひとつの姿―それも美術作品だから、視覚的なもの、つまり見た目のみの姿―の中に人々を押し込めてしまう。そして理想から外れるものに対しては矯正するか排除するかということになる。そう、ねじ伏せようと立ちはだかってくるのだ。平壌の万寿台の丘に並び立つ高さ20m以上と言われる《金日成像》と《金正日像》に、軍民を問わず多くの老若男女が献花する報道映像を見た人は多いだろう。年齢、性別、服装もさまざまな彼らは一様に神妙ではあるが晴れやかな顔をしている。これは「作られた」映像に過ぎないのだろうが、何に作られたのかといえば、それは「理想的国民」の姿にひたすらに憧れる、これもまた理想的国民の姿に「作られた」としか感じられない。
先日テレビ報道で、アフリカのいくつかの国が北朝鮮に巨像の制作を依頼しているということを知った。記念碑としての巨像。たしかにアフリカは搾取されてきた。そこから解放され、独立した。それを祝う心持ちはわかる。セネガルの《アフリカ・ルネサンス記念碑》は腰だけ布を巻いた男性が左腕に前方を指さす幼子をかかえ、右腕を後ろにいる半裸の女性像の背中にまわしている。女性像のサイズは成人しているのならば奇妙と思えるほどに小さい。ボツワナの《三首長の像》はこの国の三つの部族の首長をあらわしたもので、三人ともスーツに―つまり「西洋」の服装に―立派な体躯を包み、直立している。
男性中心・西洋中心の考え方の亡霊が、かつてそれに苦しんできた者たちにも取り憑いてしまい、それが独裁政治のもとに現れるのと同じような外見をともなってあらわれる。このような作品を見るにつけ、そして最初に語った静かにたたずむ作品に触れるにつけ、forceは人間の飽くなき欲望の対象となる力であり、弱き者に襲いかかる力、powerとはそれを求める者に働きかける力であり、弱き者の側にただある力なのだろうと感じる。
forceを追い求める者の運命は、あのスメアゴルと同じ結末に行き着くだろう。願わくば、私をどうしようもないほどに屈服させてくれるpowerを持った芸術に、これからも出会いたいものである。
ヴィットーリオ・エマヌエーレ二世記念堂、ローマ