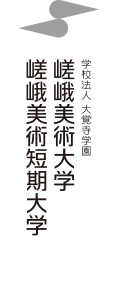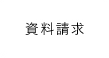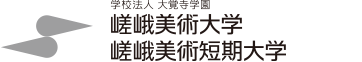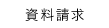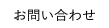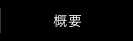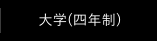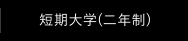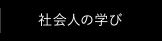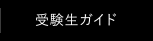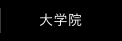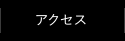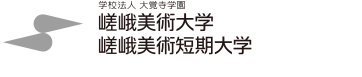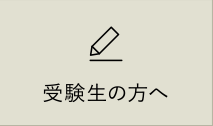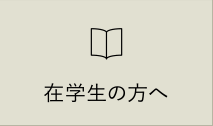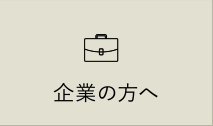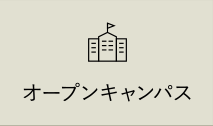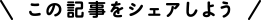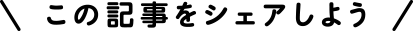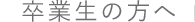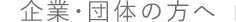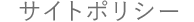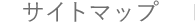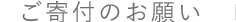「作品」をつくりだす作業が創作であり、作品を産み出す全プロセスを関心事としているのが芸術家というものである、との理解は、無難なところであろう。その最終的成果物が絵画であるか、石の彫刻であるか、あるいはテキストであれ、創作者の意思判断において完成したモノとして立ち現れたとき、表現が決着をむかえたとかんがえられる。
創作者の公表への決意をぬきにした表現は「作品」として人目にふれることにはならないのが基本である。
「表現したい」は、何かを伝えたいとほぼ同等かとおもいがちだが、必ずしも、伝える意欲をもたない表現もありうる。そのような表現者もいるのである。
ニューヨークで乳母として働きながら15万点以上の作品を発表することなく残したビビアン・マイヤーの行動は、表現の決着をどうつけるかという意味から、不可解である。それだけに彼女の創作姿勢や人生観をめぐって謎解きへの関心も高まる。ドキュメンタリー映画「ビビアン・マイヤーを探して」を観た観客は考え込むのである。
優れた写真家としてのビビアンの物語は、2007年、シカゴで暮らす青年ジョン・マルーフが、シカゴのオークションで大量の古い写真のネガを380ドルで落札したときからはじまる。彼は、その芸術的センスの素晴らしさに驚かされる。ビビアン・マイヤーがなぜ生前一点の写真作品も公表しなかったのか、その行動と人間性への興味がおおいにそそられたのである。
ビビアンは、被写体に目を合わせなくてもいい二眼レフ(ローライ)を愛用した。人物の存在感を損なうことなく捉えられたからである。こういう撮影法は、彼女のライフスタイルにも適したものであったようだ。というのは、ひととの交流を極度にきらった人物だったようだから。自己について周囲の人間にほとんど何も語らず、生涯独身で、友人もいない生き方をつらぬいた。
作品を発表するというのは、ひと(の意識)との「交流」を求める行為でもあるが、ひととの「交流」に悦びも意義も見出しえなかった彼女なら、発表が特段の意味をもたなかったと推測できる。写真を撮るという行為自体で完結していたので、それだけで十分な創造的快楽を見出していたのではなかろうか。
『非現実の王国』の著者でアウトサイダー・アーチストとしても知られるヘンリー・ダーガーも生前、作品を公表することなく生涯をおえたひととして知られる。彼についても、ドキュメント映画「非現実の王国で ヘンリー・ダーガーの謎」から、わずかにその孤立した人生の一端がうかがえる。
また、本人は作品を公表する気で創作していたのだけれど、あまりにも完成のイメージ・サイズを大きくしすぎて、達成することなく他界してしまうというケースもすくなくない。こうした場合、未完のまま作品が世に出されるか、遺された未完成品やメモなどの材料から誰かがまとめ役をはたして、本人の意志とは別に、公表に踏み切るというケースもある。
本人のけじめは、遺書に指示が残されないかぎり、本人の胸の内で、だれも知ることができない。
完成という概念も一筋縄ではいかない。百%納得のいく水準に達してはじめて完成、となれば、完成はきわめて稀な事象になるだろう。(ゼノンのパラドックス?)たとえば、ダビンチにおいては、「一作も完成させていない」(ヘンリー・トーマス/ダナ・リー・トーマス、1940)という見方があるが、こういう事例が稀とはいえない。
文芸作品では未完の秀作が目立つ。中里介山の『大菩薩峠』、チョーサーの『カンタベリー物語』、ヘミングウェイーの『エデンの園』。秀作は、欠けていても、満足度の高い芸術性を十全に備えていると評価される。
この場合、創作者自身が責任をもって「けじめ」をつけたのではないので、創作者の主体性をも含めた真正性(authenticity)が問題になる。真偽の問題を超えて、真に当人の作品といえるのか、そこも厄介だ。
ひとはそれぞれ固有の理由と感覚で創作に取り組んでいるのである。
どこまでやるか、どこで止めるか、どのへんのところをひとに見せるか、どのように創作から喜びを得ているか、それぞれに多様なのである。
芸術に没入し対面することから自己を理解するというひともいる。これは、自力の宗教者の絶対真理への欲求にも似たものといえるかもしれない。その意味で求道が芸術表現を手段とするとき、他者に伝える意欲は自然と小さくなる。
自己を理解するという人生最大の課題に創作行為が大いに有効であるとするなら、それは芸術の誇るべき力であるといえる。