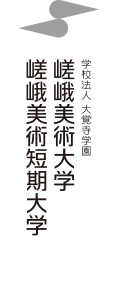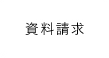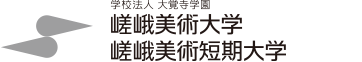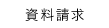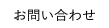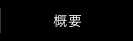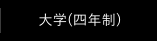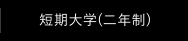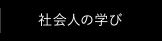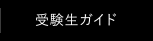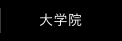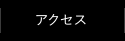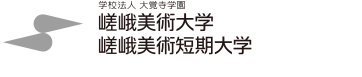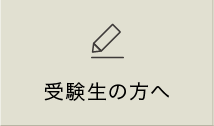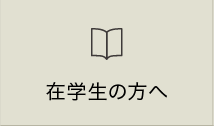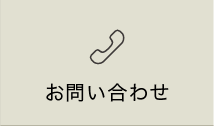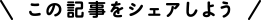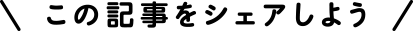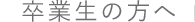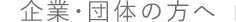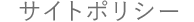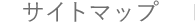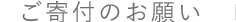ものごころついた頃から本を読まなかった日はない。これは本当だ。風呂でもトイレでも本を読む。いっかい目を通したら終わりという本もあれば、途中で放り出してしまうものもある。そのいっぽうで、何度も何度も繰り返し読む本もある。そろそろやめてもよいだろうと思うのだが、どうしても手に取ってしまう。もちろん、すでにほぼ一字一句頭に入っている。それでも読む。
「古典とは、最初に読んだときとおなじく、読み返すごとにそれを読むことが発見である書物である。」素晴らしい定義だ。20世紀最大の教養人といってもよい、イタリア文学の奇才イタロ・カルヴィーノの「なぜ古典を読むのか」という小論に登場する一節である。カルヴィーノはこうも言う。「古典とはいつまでも意味の伝達を止めることがない本である。」
さて、「古典」たりうる美術作品はこの50年ほどのあいだに生みだされたのだろうか。残念ながら私にとってはそういうものはきわめて少ない。単純にあまり見ていないだけなのかもしれない。とはいえ、美大に勤務して日々学生・大学院生の作品は見ているし、各地の展覧会ポスターは嫌でも目に入ってくる。それでも、「どうしても見に行きたい」「もう一度みたい」という衝動が起こらないのである。その理由は何か。おそらくそれは、そこに含まれる情報量によるのだろう。たとえばボッティチェッリの《ウェヌスの誕生》。描かれた神々たちは無名の人々ではない。ひとたびその神の名が知れれば、神話に登場する数々のエピソードがたちまちに思い起こされる。貝殻も海の泡もみな、なぜそこにあるのかがわかる。たとえばカンディンスキーの《小さな喜び》。漫然と眺めていたのでは、不定型な色斑と線にしか見えないが、この作品に至るまでの習作を観察してゆくと、それらが馬と旗手だったりボートだったりということがわかる。そしてそれがロシアに生まれたカンディンスキーの経験―モスクワ風景やロシア正教―と深く関わっていることまでもが理解される。見返す毎に発見があり、われわれに何かを伝えてくれる。汲めど尽きない情報が次々と発生してくる。これぞ「古典」である。
けれどもいまの私たちには、多くの人々が同じように参照でき、そこに信頼を寄せうる物語―神話や宗教―がない。それが20世紀後半の知の成果であることは確かなのだが、その成果もひろく行きわたってはいない。それどころか、いまや再び「民族」だの「国家」だのといった大戦前のあの悪夢のようなエセ物語―エセ物語が好きな方々たちは聞いたことには答えずに聞いていないことを喋ったりする。平気でウソをついて物語をでっち上げようとする。それでは意味の連鎖である物語などできるはずもない。文化庁移転を機に「文化首都・京都」を推進しよう(首都の誕生は同時に地方・辺境を生みだす。それに文化庁が京都に来たからといって、京都が得するわけではない。地域によって国が待遇の差を設けるなどということはあってはならない)と言う輩も同様だ。―が復活し始めてもいる。
もはや物語を持たないわれわれはどうしたらよいのだろうか。エセ物語に踊らされずに、芸術の「古典」を生むことはできないのだろうか。存在の金切り声(「芸術の力」18)をあげるしか道はないのだろうか。20世紀から21世紀にかけて、音楽や文学の世界ではつぎつぎと古典が生まれていると思う。何度も聞きたくなる音楽、何度も読みたくなる文学は確かに生みだされている。さて、美術は?
もちろんそれは「ある」。たとえば前回のコラムで触れた香月泰男の《シベリア・シリーズ》やベン・シャーンの《ラッキー・ドラゴン》シリーズは何度も参照される/されるべき作品だと思うし、白土三平の『カムイ伝』もそうだ。そうしたものについてひとつ言えるのは「奇をてらわない」ということかと思っている。いたずらにコンセプトを難解なものにしたり、新奇な/珍奇な技術的手段を用いたりもしない。タイトルもごく自然に内容を表している。人としっかりと向き合い、人を大切にして、素材としっかりと向き合い、素材を大切にしている。結局のところ、こうしたごくごく基本的なことをたゆまず磨きあげること、それが芸術の力を生みだすのだと思う。
以下にここで触れたり、関連したりする書物をあげておく。ぜひとも眼を通していただきたい。
イタロ・カルヴィーノ、『なぜ古典を読むのか』[須賀敦子訳]、河出文庫、2012年。
市村弘正、『増補「名づけ」の精神史』、平凡社ライブラリー、1996年。