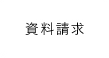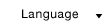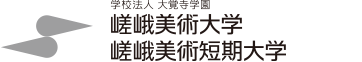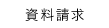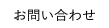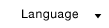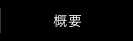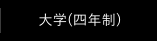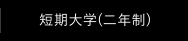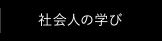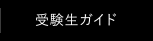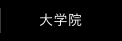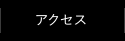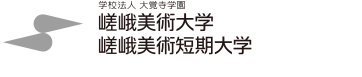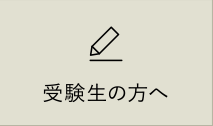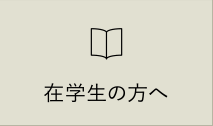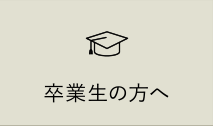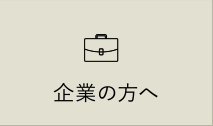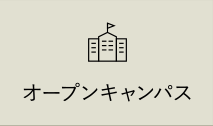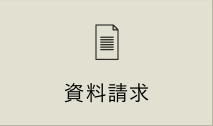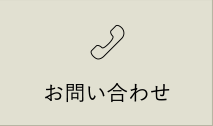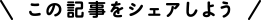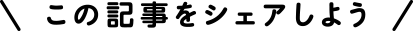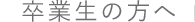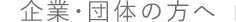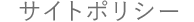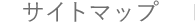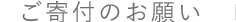「力」にあたる最も一般的な英語、powerとforceについて考える。さて、「芸術の力」の力は、powerかforceか。
forceは無理を強いる力である。強引な力。暴力、腕力。思いやりなどない。軍隊は、forceで、the air forceは空軍。平時にも、圧力を感じさせる存在である。
powerは、基本的に能力。the air powerも空軍になるが、軍事力の肯定的存在感を前に出した表現になるといっていいだろう。
英語では、もっとも身近な仕事能力という意味で、powerだけで電力を意味する。power plantといえば発電所だ。
優れた能力をもった人はpowerを行使することができるので、権威となる。能力でひとを支配できるからだ。
会社のお偉方が集う朝食会をアメリカ英語ではpower breakfastなどという。野菜サラダとハニー・ティーで清々しい朝のひとときを過ごしたい私には、「重そうな」朝食だ。
政党がpowerを持てば、the party in power(与党)となる。しかし、民意を小馬鹿にして、奢りがすぎるような政党に堕ちるとforceを乱用するようになるので国民は惨めな状況におかれる。
強制されるのがforce。抑圧の力。「力にものを言わせる」の力。そんなものが芸術の力であってはならない。だから、解放、知性などを本来の姿として発揮してもらうpowerこそが芸術の力であってほしいのだ。その意味で、このブログのテーマは、power of artとなる。

1955年に出版され、欧米でベストセラーになった『パワーか、フォースか』(エハン・デラヴィ、愛知ソニア訳、三五館、2004年)の著者デヴィッド・R・ホーキンズは、人類は「戦争、法律、課税、規則、取り締まりなどといった非常にお金のかかるフォース(そのさまざまな表現で)の手段を使って、何度も失敗を重ねてきたのです。」(前書)とフォースの悪行を指摘し、さらに「フォースは、感覚を通して体感されます。しかしパワーは、内なる気づきを通してのみ、認識できるのです。」と両者の本質的な違いを説明している。
ホーキンズ博士は、また、社会が原因の代わりに結果を正そうとばかりしていると批判する。芸術の世界でも、その種のちぐはぐが目につく。
確かに、自己礼賛の過ぎるアーティストの作品にはパワーは感じず、フォースばかりが目立って騒がしい。物質的な音の伝播はフォースによっても可能なのだが、精神の肉声はパワーによってのみ届けられるものだ。人間や社会に対する理解の深まりがパワーを産み、育てる。
イラスト:専攻科2回生 星野咲絵子さん