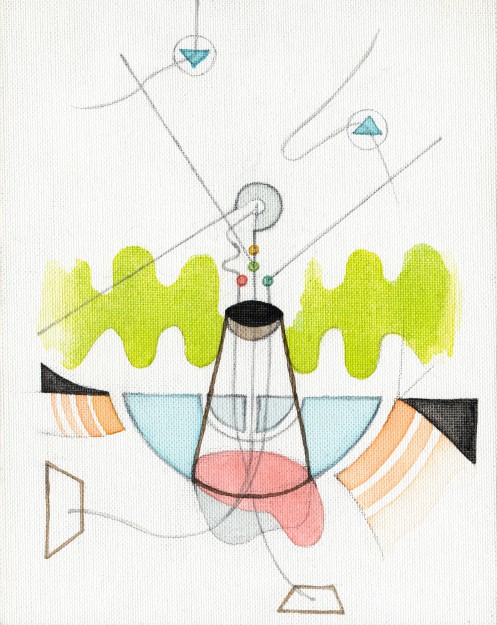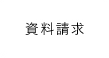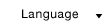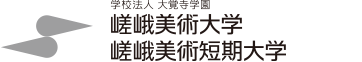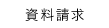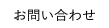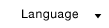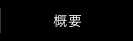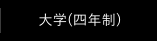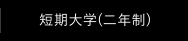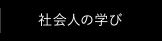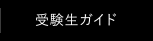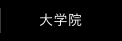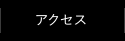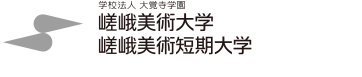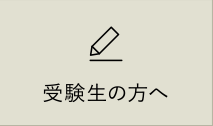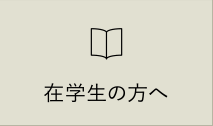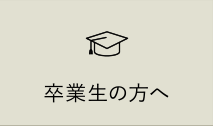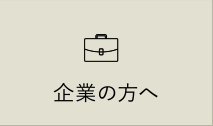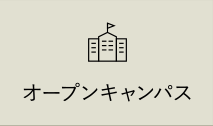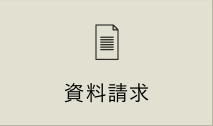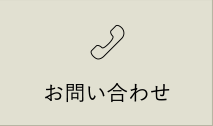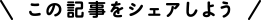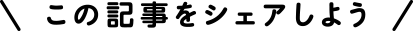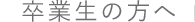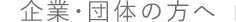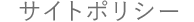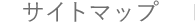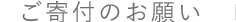頭でっかちな人類は、何はさておき、考える活動の中に、あるいは考える行為をとおして可能なかぎりの真実を見出そうとしてきた。その積年の研鑽から、目の前にある現実を、在りのままに冷静に観察するよりも、現実の見方、解釈そのものに熱意をもつようになってきたのである。
どこかのだれかの「オモシロい見方」にいたく感心する。そうすると、どうしたことか、その見方が指示している内容と真実との関係を慎重且つ真剣に問い正す作業は脇に置き、「見方」にぞっこん魅了されてしまう。これが頭脳の性癖なのだ。
子供たちも、言葉を学ぶころには、なにかに出会えば、直ちに「解釈」や「感想」が飛び出すことを求められる。思考の活動を即座に確認したいという習性が出来上がっているのだ。
“現実そのもの”、“真実そのもの”よりは、「解答を求めて考えるという作業に取り込む方が実際的ではなかろうか」と、あくまでも考えの中で決着をつけようとする。いわゆる言い訳は、思考上の折り合いをつける他愛のない工夫だが、科学や法律の世界にも蔓延っている。こんな事情から、言葉の巧みさが、現実や真実から切り離されて賞賛されるのも珍しくはない。
芸術が分かるか、分からないか。それを知識の差としたり、経験の深浅としてしまうとき、考えの程度を問題にしているのであるが、芸術の本性の理解からは逸脱している、とおもえる。何よりも、思考の前に、芸術そのものに向かい合う意識を全開しなければならないのである。芸術として現れている「対象」の実在の姿を直視し、怠りなく、観察し、賞味し、吟味しなければならない。観察者自身のリアリティに対する個別な関わりを御座なりにして、既存の言説の追随にかまけることなく、直接に対象に出会わなければならない。考えだけをめぐらせて「対象」を見ないのは、アイマスクを付けたままで、色や形状を点検しようとするようなものである。
要するに、思考は、対象を見ずに見解を産みだそうとする。この欠点は、皮肉なことに、想像力のバネとしても機能するので、状況によっては、特段に評価される働きでもあるのだが。
さらに、思考の決定的な欠点は、考える対象を特定すると、ただちに、それとそれ以外にバッサリと切り分け、現実という世界をバラバラに断片化してしまうことである。(「世界」という語は、そもそも現実そのものとは関係のない記号でしかないのだが、既に、ここに思考の一人芝居がある)「全体を考える」という表現は、ひとがそのようにやってみようとする気になるものの、それを思考が支配しているかぎりは実現しない出来事なのである。都市計画や幸福なコミュンづくりがうまくいかない根本原因はそこにある。
「リンゴを描いた絵」がある。何を描いているかは分かる。しかし、その作品の芸術としての価値が分かるのとは別の話である。ぐうたらな親爺が描いた絵だから表現動機は知れたものだ、と即断することもできない。技法として、上手か、下手か。どちらの判定に至ろうとも、それで、その絵の芸術としての価値を明らかに示せたのだろうか。ましてや、描かれているリンゴが紅玉であって、断じて王林ではない、との判別は、この絵画のモチーフの特定に関するかぎり「正しく」ても、その作品の表現のもたらす価値評価を下すには至っていない。そう断じている当人の内にある知識との交流は存在するのだろうが、作品との交流はない。
知識は、それ自身が思考の部品として活発に働きながら、認識の全体に関わりきれず、全体像を断片化してしまうのである。知識はリアリティにシンクロ不能な過去の”結晶体”なのだから仕方がない。
「相手の気持ちが分からない」と、愛する相手のこころに困惑しているひとがいる、とする。
その気持ちが読み取れない、というので思い切って相手に問いかけた。「ぼくが好きですか?」。
さて、当人も「分からない」との返答だと、「ぼく」は頭をかかえる。
ひとのこころの現実は、二択で理解されるものではない。それくらいの知識は中学生でももちあわせているが、思考で愛をとらえようとすると、乱暴にも、成功か失敗かという二択問題になってしまう。
芸術作品を目の前にして、「分からない」と頭脳が言ったら、理解への願望を捨て、作品との交流に「こころ」を投げ出し、知識の負荷のない意識に任せてみようではないか。
イラスト:専攻科2回生 星野咲絵子さん