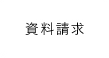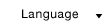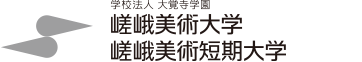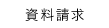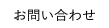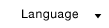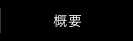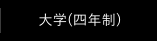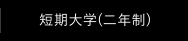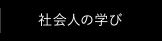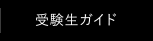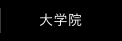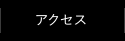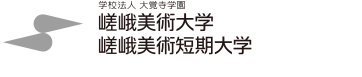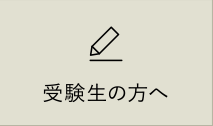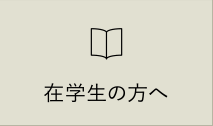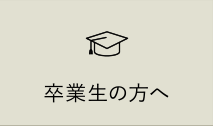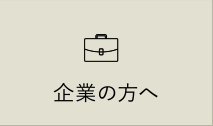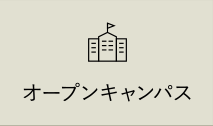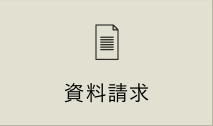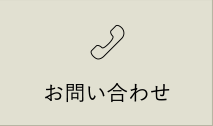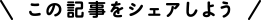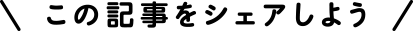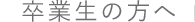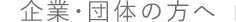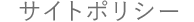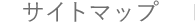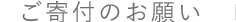喫茶店などで出されたカップの一部がほんの少しでも欠けていると、コーヒーなり、紅茶なりの味が上等でも、ちょっと寂しくなるものだ。
その店に対する評価が、カップの小さな欠損によって一気に下落してしまう。
前の客がこぼした水がテーブルトップに残っているのもたまらなく不快だ。拭く手間を欠くという怠慢が、そういうかたちになっているとおもえて、心地好くない。
器の欠損が、あるいは、注意の欠損が、信用の欠損となる。
美を考えるとき、欠損はどういう意味をもつのだろうか。一部が欠けたカップは、美しいか、美しくないか。
その欠けた部分をのぞく、他のすべてが完全にととのった姿をもっているカップにおもえるなら、その「欠け」は、ととのっていない部分という印象において、美を損なう唯一の要素、つまり美の対極にある醜そのものを示すサインに見えるだろう。おそらく、こういう見方については、ごくふつうな生活感覚に通じる当然なものであり、記述する必要もないはずだ。
完全なものが美しい、というベースがある。それを損なう「欠け」や「しみ」や「ひび」などは不完全な要素になる。
完全を美の本質とする見方は、感覚的にも理性的にも分かりやすい。けれども、完全というものがどういうものなのか、となると、分かりやすい話ではない。すでに、以前のブログで述べたように、分析という思考方法では「全体」は把握出来ないのだ。
真っ白なカップに、黒い点がひとつある。汚点に見える。意図をもって置かれた点ではなく、うっかり付着してしまった点と見られれば、確かに汚点となる。
黒い点が、一定の大きさをもち、しかも多数あり、カップ全体に調和をもって配置されていると、これらの点は装飾的な要素として心地好い機能を果たしている、とみなされるだろう。黒い多数の点は全体の見え方を変容させてみせるものだから、完全なカップをうみだす仕事をしているともいえる。
「完全」は、「全体」を引き連れている、と考えられないこともない。
茶人千利休は、見た目の「完全」、考えた(意図した)とおりの「完全」を最上に置かないという美の評価を流儀にしたひとである。また、値がはれば美の程度も高まるというわけでもない、という当然なことを、利休は選択眼と扱い方の尊重において示そうとした。
一輪挿しの竹筒に、ちょっとした割れが入っている。その物理的な不完全さにおいて、安定しきれない、小さなざわつきの残る心的状態がうまれる。この不完全さによって穏やかな躍動が生じる事実に利休は着目していたのだろう。
「完全」のもつ美は静的(static)である。一方、「不完全」のもつ美は動的(dynamic)である。そして、「不完全」は「全体」の一部を損なっているのである。
「ルーブルには、顔の部分がひどく摩耗した肖像画がある。それにもかかわらず、どういうわけか、その作品の価値は損なわれていない。たしかに瑕はあるが、大した問題ではないのだ。
その絵はティントレットの作品である ——— 彼も偉大な巨匠だ。形体の構成力があまりにも力強いので、摩耗したところからでも力が伝わってくる。」ロバート・ヘンライ『アート・スピリット』(野中邦子訳、国書刊行会、2011)
一部に欠けがあったり、不鮮明なところがあっても、「構成力」がしっかりしていると何の不具合もなく、観る者に、その絵画のメッセージが十分に伝わってくる。
「摩耗したところ」を、鑑賞者は自らの見方で補っているのだが、それは作品への参入でもある。鑑賞者の脳内で創作された補完部があってこそ、「全体」が成り立ち、鑑賞者における「完全」が現れてくるのである。
とはいえ、「完全」な姿を脳内で再生することと、そこに美を感じることは同じではない。
ミスユニバースの美と大衆食堂のおかみさんの美という事例で考えてみたらどうだろう。みごとに整った造りの美女に、一定の美を感じるのだが、その美は満足度の高い美ではない、という場合もある。一方、「美女」とはいいがたいものの、得体の知れない好印象が、その女性を途方もなく美しく感じさせる場合もあるのはなぜだろうか。
見掛け上の「完全」を損なう要素を帳消しにする、より上位の評価水準があって、そこで働く評価の眼が作品なり人間なりを鑑賞しており、そこでは物理的な欠損は欠損性を失い、「完全」を取り戻しているのであろう。(あるいは真の「完全」をやっと見出した)
ここには、われわれ人間の意識の特別な作用が関わっているに違いない。この探求は次回にまわしたい。